音楽鑑賞の備忘録。
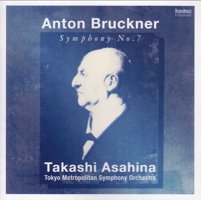
- 朝比奈隆 (指揮)
- 東京都交響楽団
- 2001年のライブ録音
アンサンブルは、精度の点でも、表現の細やかさの意味でも緩い。音を出しているパート数が増えてくると、中低音域の響きが混濁し初めて、雑然と響いてしまう。パート間の音のバランスも大雑把な印象。オーケストラの響きを敏感に聞き分ける耳の持ち主には、耳障りな場面が少なからずありそう。
東京都交響楽団に詳しくないのだけれど、2001年というと、インバルとかベルティーニらとすでに仕事をしていた時期。だから、もっと上手にできそうな気がする。個々のパートに注目すると、いい感じに聴こえるし。
指揮者の統率力に不足があるのかもしれない。
とは言いながら、己れの弱点に拘泥しないで、ひたすらに自分の音楽をやっているという一途な様は、巧拙とは別の意味で響いてくる。
リズムの支えの上に響きを構築していくというより、フレーズの歌わせ方とか息遣いとかの横の流れで進めていく。それも、各パートの線の流れが混然となって一つの流れを形作っていく。堂々とした足取りとか厚い響きがあいまって濁流気味の大河の流れ。
彫りは浅く、肌理は粗く、立体感も乏しいけれど、あるがままと思わせるような、自然な佇まいがある。
そして、フレーズをニュアンス豊かに息づかせる、ということについては、とてもセンスがよいと思うし、気持ちがこもっている。音楽の息遣いが直接的に伝わってくるような心持ちがして、何度かハッとさせられた。
これより上手い演奏が、同じだけハッとさせてくれるとは限らない。
この交響曲を代表する名演とは言い難いながら、他の演奏では聴き逃していたかもしれない楽曲の魅力を、気づかせてくれるかもしれないという意味で、手元に置きたい演奏と思う。
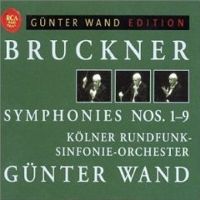
- ギュンター・ヴァント (指揮)
- ケルン放送交響楽団
- 1980年のセッション録音
ケルン放送交響楽団の響きには柔かく広がる感触があるけれど、ヴァントの作り出すフォルムその物は強靭に研ぎ澄まされている。
高弦のフレージングは曲線的でスムーズに連鎖していくけれど、雰囲気に流れることは全くなく、芯が通っていて的確にコントロールされている。
作品の書法を明解に、メリハリよく描き上げながら、ブルックナーが狙ったであろう効果の読みを、合理的な範囲で(何が合理的なのかはともかくとして)加味したような感じ。
作品のあり方全般に行き届いた演奏と思うけれど、神経質なまでに目配りされたアンサンブルの洗練と緊張感が強く訴えかけてくる。
艶っぽさは乏しいし、色数が多いわけではないけれど、手持ちの素材を徹底的に磨き上げている印象。
第二楽章の聴き所は、気分とか雰囲気ではなくて、高弦の精緻なアーティキュレーション(音の形を整え、音と音のつながりに様々な強弱や表情をつけること)がもたらす細やかな表情の数々だと思う。
言い換えると、アンサンブルの緊張感が強く出ているために、気分や雰囲気には浸ることには向かない。
このあたりに、この演奏ならではのテイストを感じる。
交響曲としての構成や作品の書法に向き合いたい聴き手には、この演奏の密度と精度の高さが、しっかりとした手応えになりそう。
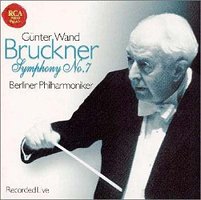
- ギュンター・ヴァント (指揮)
- ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
- 1999年のライブ録音
小理屈をこねることがはばかられるような、吟味し尽され、磨き上げられた演奏。
演奏の特徴は、過去に取り上げたケルン放送交響楽団とのセッション録音に近い。
高潔なまでの秩序とか調和に基づきながら、曲線的に連鎖していくフレーズは雄弁。見通しの良さを堅持しながらも、その範囲ぎりぎりまで豊かに広がるサウンド。
さらに、ケルン放送交響楽団とのセッション録音にあった、神経質さや緊張感がほぐれて、ゆとりとか余裕が感じられる。アグレッシブさが薄まることが、常に良い効果をもたらすとは思わないけれど、この交響曲に関しては好感触。
柔かな中にも光沢とか艶を聴かせるところは、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団らしいのかもしれない。もしかしたら、そういうところがヴァントらしさを弱めているのかもしれないけれど、この演奏を聴く限りでは、賛辞しか思い浮かばない。このオーケストラの性能と表現力の高さが音楽の魅力に直結している感じ。
第二楽章では、「この楽章の美しいポイントがこんなにたくさんあったのか」と目を見開かされる思い。幻想的な音響効果ということより、フレーズの流れが織りなす間合いの妙味を、滅多に聴けないくらいに鮮やかに示してくれる、という感じ。この点だけで、十分に離れがたい録音。
第三楽章では、整然と進行させながらも、雄渾な広がりに胸がすく思いだし、かと思うと中間部のニュアンス豊かな歌が心地よい。
ヴァントは、負の情緒につながるような表現をしない、もしくはそれをするのが不得手。その印象はここでも変わらない。むしろ、オーケストラの発色の良いサウンドのせいで強化されているかもしれない。そのために、この曲の演奏としては、陰影めいた要素は乏しくて、明朗に聴かせる。
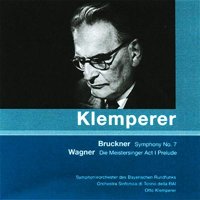
- オットー・クレンペラー (指揮)
- バイエルン放送交響楽団
- 1956年のライブ録音。モノラル
ほどほどにノイズを取り除いて、音の見通しを向上させて、空間の雰囲気を醸し出す、くらいに手が加わっていそうな音質。録音年代を考えると、とても聴きやすくなっている。
滔々たる流れに身を委ねたいとか、瞑想的な気分に浸りたいというような要望にはまったく応えてくれない演奏。
クレンペラーの作り出す音楽は堅牢で豪壮。造形の外枠はガッチリしているし、フレージングの折り目もきちんとしていて、気分に乗って横に流れることはない。各声部が積極的にブレンドされることもない。盛り上がりでは心持ちテンポアップされるけれど、堅固な相貌。
しかし、ゴツゴツと剛直なだけの音楽をやっているわけではない。
堅牢な外枠の内側では、バイエルン放送交響楽団の特性を活かして、端整かつまろやかなアンサンブルが繰り広げられている。高弦の線の流れには上品な艶が感じられるし、柔かく広がるサウンドがガッチリとした造形を押し包んでいる。
そして、造形に揺るぎを感じさせないけれど、音楽の呼吸をはっきりと意識させる。楽曲と距離を置いているようでありながら、突き放した印象を与えないどころか、息吹を感じさせる。
ここのところのパランスは独特と思う。
魅力的なフレーズの連鎖や豊かな音響に耽ることはないから、聴き方によっては素っ気ない作品解釈ということになりそう。
しかし、クレンペラーとしては気持ちの入った演奏と感じられる。
この作品のフレーズや音響の美しさを斟酌つつ、その上で音響構造体としての威容を描き出そうとしている、ように聴こえる。
重厚に聳え立つフォルム、直線の主体の中に巧みに曲線美が配された意匠。壮大なゴシック建築を連想させられる。
そして、そのように感じられることについて、バイエルン放送交響楽団の役割は大きいと思う。

- セルジウ・チェリビダッケ (指揮)
- シュトゥットガルト放送交響楽団
- 1971年のライブ録音
シュトゥットガルト時代の正規録音の中でも録音年代は古いけれど、放送局所蔵の音源ということで、鑑賞には十分な質のステレオ録音。
この交響曲の、音響構造体としての美しさを存分に引き出そう、というような演奏。透明度が高くて量感のあるサウンドが、自在に伸縮しながら、美しく歌い上げていく。
そして、美しい一辺倒ではなく、響きの美観を崩さない限度にドラマティック。
瑞々しい音響美と情熱の両立を狙っている感じ。
晩年のミュンヘン・フィルとの一連の録音と比べると、響きの量感は薄め。響きの透明度の高さが、そういう印象を強化しているかも。そのぶんテンポも流暢。
もっと厚ぼったい響きの方がブルックナーらしく感じる人はいるかもしれない。
でも、適度なテンポで、豊かに響かせながら、オーケストレーションを鮮明に浮き上がらせるなら、程好い仕上がりと思う。
しっかりと自分の音楽をやりつつも、己れの体臭で楽曲を染め上げるのではなく、楽曲の展開に素直に則っている感じが好印象。
チェリビダッケの毒気を好んで浴びたい聴き手には薄口かもだが、この交響曲を、美しく、わかりやすく、色彩豊かに聴かせるという意味では、いい塩梅だろう。
崇高とか、宗教的な雰囲気めいたものは乏しいと思う。練られた表現だけど、ストイックとは正反対に、響きとかフレージングのニュアンスに浸るよう。聴き手の作品観によっては齟齬が生まれそうだけど、音楽の悦楽に素直に向き合っているとも言える。個人的には好感を持てる。
チェリビダッケのシュトゥットガルト時代のブルックナーの中には、オーケストラの技量に不安を覚える録音もあるけれど、この録音はまずまずの出来ではないだろうか。
(2014-8-2 投稿)

- コリン・デイヴィス (指揮)
- バイエルン放送交響楽団
- 1987年のライブ録音
この演奏では、4つの楽章が通常とは異なる順番に演奏されている。
第1楽章 → 第3楽章 → 第2楽章 → 第4楽章
の順。ブルックナーにありがちな版の問題とは無関係に、デイヴィスの判断でやっているらしい。
演奏後に拍手の模様が若干収録されていて、盛大な拍手と混ざってブーイングもけっこう聴こえてくる。
この演奏順で聴いたところ、個人的にはなかなか好印象。
が、せっかくのデイヴィスの創意なのだけど、音盤で鑑賞する場合、再生順を聴き手の好きにできることもあって、鑑賞する上での決定的なポイントとは感じていない。
この交響曲の美質が、高いレベルでスーッと入り込んでくる演奏と感じた。
デイヴィスの表現力もさることながら、バイエルン放送交響楽団との協演であることが大きいような気がする。後のロンドン交響楽団とのブルックナーとはかなり印象が異なる。デイヴィスは、自分の持ち味とオーケストラの持ち味を完璧に両立させるツボを見出している感じがする。
デイヴィスはフレーズの線をくっきりと整える傾向だけど、オーケストラは高い機動性でその要求に応えつつ、暖色系の柔らかい響きでもって心地よいブレンド感を加味している。この端整さと豊かさの配合が絶妙に聴こえる。
ここでのデイヴィスは、端整な相貌に崩すことはないけれど、その範囲でダイナミックにやっている。深い息遣いを聴き手にはっきりと意識させる。抑揚はかなり深くて、リズムとかフレーズの一つ一つにしっかり体重が乗っている感じ。
デイヴィスの演奏をそんなに聴いていないのだけど、全身で呼吸するような深い息遣いを聴かせる指揮者、というイメージを持っていなかった。むしろ、逆のタイプと見做していただけに、この表現は意外。
一般的な意味での「情熱的」という言葉からすると控えめだけど、かなり気持ちの乗った演奏と感じられる。
アダージョは荘重で豊かだけど、瞑想的な雰囲気とは違う。音楽の一挙手一投足に明確にニュアンスが込められている。でも、生々しくはならない。デイヴィスの端整をバイエルン放送交響楽団が豊かに包み込む、みたいな組み合わせが効いていると思う。
そして、深くて自然な息遣い。
スケルツォやフィナーレは、キリリとしたダイナミックな表現だけど、荒さや粗さや硬さは感じられない。主題の対比が鮮やかで、そしてやっぱり自然。爽快。
4つの楽章の演奏順のことを別にできれば、この交響曲を形作るいろんな要素が、満遍なく、バランス良く目配りされた演奏と思う。