音楽鑑賞の備忘録。

- ヘルベルト・フォン・カラヤン (指揮)
- ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
- 1982年 ライブ録音
楽曲の構成とか書法の扱いについては、至極真っ当に聴こえる。その上で、気持ちが入っていて、力感や大きさも兼ね備えている。ここまでなら、模範的なくらいにまとも。
しかし、引っかかりのない流れるような歌わせ方とか、しっとり系の透明感を湛えた厚いサウンドとかで、独自の境地に落とし込んでいる。
個々のパートは、輪郭をなくさないギリギリのところまで甘い。それぞれの線の動きは流れるようで、個々を識別できるけれど、全体の豊麗な響きの中に融合しているような、サウンドイメージ。なめらかにブレンドしている反面、一つ一つの線の実体感は薄め。
総体としての響きの厚みからすると、驚くほどの透明度だけど、抜けるような透明感とは違う。フレーズの動きを、控えめにふるわせたり、泣かせたり、しならせたりしながら、ほどよく湿度を加味していく感じ。
そうした流儀嗜好の徹底により、結果として作品書法とか感情表現はあいまいにぼかされた感じに、悪く言えば骨抜きにされている。
繊細な表現から、スケール豊かな高揚まで、表現の幅は広いけれど、響きの質感は一貫して保たれている。それゆえに、そうした質感こそが、この音源の最も強い特徴として意識される。
楽曲の形はできるだけ真っ当に描き出しながらも、色づかいに自分の美学を全面的に打ち出して、結局のところ、カラヤン臭の濃い音楽になっている、と思う。
おそらくカラヤンとしては、"美しい"サウンドとして、こういうやり方をしているのだと思う。聴き手も"美しい"と感じられれば、カラヤンの流儀は見事に成立する。しかし、"美しい"と感じられない聴き手には、妙に癖の強いサウンドとしか意識されないかもしれない。
あるいは、"美しい"と認めることができても、マーラーの第9交響曲について、この種の"美しさ"に価値を見出さない人がいるかもしれない。当然、この逆もあるだろうし。
カラヤンの美意識が結晶化されていて、演奏の質は優れているし、一気に聴かせるような勢いも感じられる。演奏芸術としてのレベルは極めて高いと思う。

- デイヴィッド・ジンマン (指揮)
- チューリッヒ・トーンハレ管弦楽団
- 2009年 セッション録音
各パートの線の動きのひとつひとつを際立たせるより、まず広がりのある音楽の流れを作り出して、その中で場面に応じた表情を作り出して行く感じ。ボリュームのバランスでは弦群がやや優位に聴こえるけれど、アンサンブルとしてはそれぞれのパートを鳴らし分けながら、ホールの響きを豊かに取り入れることで、一体とした響きを作り出している感じ。
余裕のあるテンポで、楽曲の展開をじっくりと聴かせるけれど、複雑なオーケストレーションをすっきりと整理して、気持ちよく響かせる。また、各声部の歌い回しは伸びやかでスッキリ。粘度は低い。
それらがあいまって、豊かに響き渡りながら、ひっかかりなく流れていく。
対位法的な構図を聴き取ることはできるけれど、ひとつひとつの線の芯が弱いので、線と線が多様にからみ合うというより、サウンドの多彩さ、華やかさとして表れているような感じ。
結果として、対位法の醍醐味みたいなものは薄らいでいるように聴こえる。
その一方で、音楽の展開はすっきりとわかりやすくなっている。4つの楽章のキャラの差異がほどよく丸められて、良くも悪くも引っかかりなく聴き通すことができる。この交響曲を聴いていてしばしば感じるジャジャ馬感はほぼ払拭されている。
この大曲をわかりやすく展開させて、彩り豊かに響かせる、というところに的を絞り込んだような演奏と思う。そして、その限りではうまくやっていると感じる。
ただし、それ以外に、この交響曲のこの演奏でしか味わえない何物かが提示されているかとなると、ちょっと思い当たらない。骨組みと表面加工にもっぱら力を尽くしている感じ。
他と比べると味が薄く感じられるけれど、そのやり方によって、全曲がしっくりとまとまって聴こえるとしたら、この交響曲を難しく聴かせる演奏の方が、こねくり過ぎているのかもしれない。

- レナード・バーンスタイン (指揮)
- アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団
- 1985年 ライブ録音
複雑な作品書法を、明解かつリアルに響かせるという意味ではきわめて強力。バーンスタインは、すべてのパートをニュアンス豊かに奏でさせながら、それらを精密にバランスさせる腕を持っていて、この演奏ではその腕力が最高度に発揮されていると思う。すべてのパートが生々しく蠢き、作品書法が剥き出しのように聴こえてくる。しかも、オーケストラの持ち味のおかげか、そうした感触が聴き苦しさにつながらない。
その裏腹に、複数の声部を連動させて、色合い豊かな一つの流れに収束させるとか、溶け合って一体として響かせる、みたいなことはやらない。響きの色彩感とか重層感みたいな感覚とは馴染みにくい。
響きのブレンドの加減で表情を作り上げる、みたいな作法とか別の次元でアンサンブルをやっている、ということなのだろう。巧拙とは別のこと。
そういう彼のスタイルが、第1〜3楽章では良い形で働いている、と思う。剥き出しの生々しい真実を突きつけるような、シリアスな味わいの音楽が出来あがっている。
容赦なく音を剥き出しにする響きへの感性と、濃密な表情の造り込みは強烈に個性的で、好悪は分かれそうだけど、楽曲を完璧に消化している感じ。解釈がどうのこうのと言う前に、手練手管を弄しない真っ向勝負の凄みに、納得させられてしまう。
息の長い旋律が連綿とする終楽章で、バーンスタインは、ゆったりとした足取りで、目一杯深く歌い込んでいる。線を解きほぐし、細かい襞の襞まで描き出そうとする意志が伝わってくる。反面、粘着の度が過ぎて、音楽が一つの呼吸で歌われている感覚はいささか後退している。
この楽章はかなりシンプルなので、ここまで粘着しなくても、すみずみにまで光を当てることは可能と思う。そういう意味では、意味があってやっているというより、やりたいからやっているという感じ(それが悪いということではない)。
もっとも、そうすることによって終楽章が第一楽章に匹敵するくらいに巨大化するので、交響曲全体としての柄が一回り大きく感じられること。それが作曲者の意図に近づくことなのかはともかく。
いずれにしても、音楽によるシリアスなドラマという方向性でこの交響曲を聴くなら、並外れて迫真性のある演奏だと思う。わたしはバーンスタインの良い聴き手ではないけれど、この演奏には畏敬を覚える。
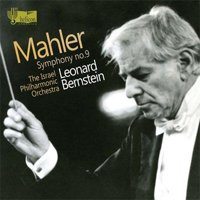
- レナード・バーンスタイン (指揮)
- イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団
- 1985年 ライブ録音
イスラエル・フィルのレーベルHelicon Classicsによる実録ライブ。
各パートをニュアンスたっぷりに奏でさせつつ、そのすべてを生々しく浮かび上がらせる、というようなアンサンブルの作り方。
音楽は生々しい表情を帯びるのだけど、その一方で、サウンドの総体としては、濁りがちだったり、煤けているように聴こえる。
気合のあまりところどころそうなるのではなく、一貫して混濁気味。サウンドの制御に関して、この交響曲にふさわしい水準にあるとは言いにくい。
アンサンブルの調和がもたらす和声の妙に息を飲む、というような瞬間は、おそらく皆無。
にもかかわらず、バーンスタインは強いカリスマ性で楽員を掌握している模様。バーンスタインの指示によると思われるのだけど、心の震えをそのまま音に置き換えたような生々しい表現を、強い集中でもって繰り広げている。
ただし、イスラエル・フィルの柔かくて淡彩な響き(録音のせいかも)が生々しさを抑える方向に働いているように聴こえる。
そのせいか、感情移入がストレートに訴えかけてくるというより、怨念となって立ちこめるような風情。上述した淀んだ響きがあいまって、負の感情が鬱蒼と渦巻いているような。
ある種の凄みを感じるけれど、聴き苦しい演奏ではあると思う。

- ジョン・バルビローリ (指揮)
- ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
- 1964年 セッション録音
フレーズの一つ一つの動きと、それらが連鎖する様を明瞭に浮かび上がらせる。盛り上がる場面でも、金管など大きな音を出すパートをコントロールして、線が絡まり合うようなサウンドイメージを貫いている。
第1〜3楽章では、音響が塊状になることがなく、徹底して対位法的。さすがに終楽章は量感豊かに歌い上げられていて、一体とした響きの中で進行するけれど、漂うように、あるいは茫漠と広がるのではなく、フレーズに芯が通っている。
対位法の線の動きにこだわりながら、それぞれの線の動きには粘りがあって、色合いには深いツヤがある。特に、ヴァイオリンの多彩な歌わせ方は印象的。弦群は当然として、金管群にも柔軟な抑揚を要求している。というか、打楽器以外のすべてパートに濃く深く歌い上げることを要求している。
やはり、歌うことが得意な楽器の方が目立ちがちなので、弦楽器優位の演奏に聴こえるかもしれない。
即物的な響きは皆無だし、音の激しい交錯の中であれよあれよと言う間に進行される、ということもない。また、粘っこく歌い込んでいるけれど、響きの見通しはよいので、息苦しさに辟易させられることはないと思う。しかし、執拗さは感じる。
力強さは必要十分だけど、暴力的な大音響とか、スリリングな展開、みたいな刺激性を求めて聴くような音源ではない、と思う。また、濃厚な歌いっぷりだけど、楽曲を情念のドラマとして描き上げているわけではない、と思う。濃密な歌い回しは、ある意味この指揮者の体質みたいな感じ。
楽曲を形成する点や線を丁寧に扱い、作品らしさを確保しながらも、バルビローリの色に染め上げている。それも、艶はあるけれど渋い色調に。こだわりの美学を聴くことができる。

- ピエール・ブーレーズ (指揮)
- シカゴ交響楽団
- 1995年 セッション録音
情念とか妄念の気配をキレイに拭い取って、壮麗なサウンドイメージを聴かせる。
フレーズの一つ一つは、柔かくてしなやかで透明度が高い。そして細身。それらが端正かつ親密に連鎖してアンサンブルを作り上げていく。金管群も野太い威嚇音は厳禁。典雅で小気味よい表現。
オーケストラが発しているサウンド自体は、スッキリとして繊細な質感の響きと思われる。しかし、録音会場のたっぷりとした音響特性が存分に活かされていて、最終的には清涼かつ壮麗なサウンドイメージが、スケールたっぷりに展開されている。
明るい色調のしなやかな繊細感が支配的だけど、盛り上がる場面では、ホールの空気のすべてを揺るがすような量感。しかし、威圧的な響きや重苦しさは一切ない。
作品の描き方としてはある種の偏りを感じるけれど、表現の幅は大きくて、かつ洗練されている。格の高い芸であることは疑いようがない。
響きの繊細感は強いし、精密なアンサンブルが繰り広げられていることは伝わってくる。しかし、骨のないフレージングとか、量感たっぷりな響きのせいで、ディテールの明瞭さはほどほど。
ディテールを作り込みながらも、そこで勝負をするのではなくて、音響美とかサウンドイメージを聴かせることに軸足を置いているみたい。
結果として、ラモーのオペラとか、ラベルの「ダフニスとクロエ」なんかを連想させる、典雅で壮麗なサウンドイメージが出来あがっていて面白い。といっても、フランス風のマーラーをやろうということではないだろう。この交響曲を華やかな管弦楽法の精華として格調高く響かせる、というコンセプトのように聴こえる。ただ、管弦楽法の多様性を、色彩感の多彩さとして軽やかに表現しているところは、もしかしたら優れてフランス的なのかもしれない(わたしはフランス通ではないので、想像しているだけ)。
4つの楽章の関係は大規模な組曲といった体で、ここまでにマーラーが獲得した語法をバラエティー豊かに披露している感じ。ドラマ仕立ての演奏を期待して聴くと、面食らいそう。

- ガリー・ベルティーニ (指揮)
- ケルン放送交響楽団
- 1991年 ライブ録音
マーラー交響曲全集から。
ほどほどに緩急をつけて活気を出しているけれど、呼吸はそんなに深くはなくて、身振りもさして大きくない。力強さに不満はないけれど、落ち着いた足取りで、複雑な作品書法を平明に整理して、いたってわかりやすく聴かせる。
ほどよい量感を保ちながら、しなやかに、スムーズに、明解に展開させていく。粘りはそれなりにあるけれど、フレーズのフォルムはキレイだし、響きの見通しもいいので、息苦しさは皆無。
各パートを表情豊かに響きかせながら、それらを親密につなぎ合せ、織り上げていく感じ。すべての音をあるべきところにピタッと収めていくような感じ。サウンドも、各パートの輪郭がボヤけない範囲で、マイルドに溶け合わせて、豊かに響かせる。
おかげで、この交響曲のオーケストレーションを、複雑で入り組んでいるとしても、過剰とか騒がしいとは感じさせない。
いたって明解な立ち振る舞いを通して、そのように感じさせるので、作品の有り様を素直に映し出しているように聴こえる。
そんな練られたアンサンブルを基調にしつつ、各楽章の味わいを高めるように展開させる。突き抜けた要素は見当たらず、異次元に誘ってくれる演奏ではないかもだけど、やっていることは上質で、よく練られて、融和した音楽に浸ることができる。刺激的成分より、居心地の良さが魅力かも。
いずれにしても、音符に込められたニュアンスとか、それらのつながり方とか、響きの重なり方とかの、部分の作り込みにかんしては強い説得力を覚える。上手い演奏という以上の価値を感じる。この交響曲がどんな音楽かを確認するために聴く演奏という意味では、高位にあるかもしれない。
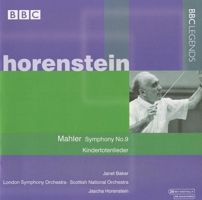
- ヤッシャ・ホーレンシュタイン (指揮)
- ロンドン交響楽団
- 1966年 ライブ録音
BBC LEGENDSの1枚。ステレオ録音らしいのだけど、空間の広がる感覚は乏しい。
余裕のあるテンポ。透明度が高くて見通しの良いアンサンブル。それぞれのパートの表情は十分に施されているし、リズムやテンポの揺さぶりなんかも聴かれるけれど、総合的には、構図の明解さとか、質のそろった響きとかが優先されていて、多彩なニュアンスが溢れ出してくるようなやり方ではない、と思う。
作品の複雑で大規模な構成とか書法を、明解に、大きなスケールで描き出そう、というようなアプローチと思う。
そういうアプローチをしながら、実録ライブならではの、凄まじい覇気を聴かせる。第1〜3楽章は言うまでもなく、第4楽章でも、迫ってくるような力のこもった歌いっぷり。
ただし、前のめりな覇気ではなく、ベテランらしく、音楽の展開にテンションをのせていく。激しさゆえに、アンサンブルの精度は劣化しているけれど、広々としたサウンドイメージが揺らぐことはないし、多様な展開に的確に応じている、と思う。
とは言え、上に書いた通り、多彩なニュアンスで聴かせるスタイルではないから、攻撃的なところが際立って、潤いとか細やかさは乏しく感じられる。また、要所要所は押さえているとしても、アンサンブルに精妙な味わいは乏しい。刺々しく聴こえる場面も少なくない。録音の影響も大きいような気はするけれど。
ホーレンシュタイン自身は、この交響曲をすみずみまで吟味し尽せているけれど、ここでは敢えて、細部を作り込むことより、劇的な音のドラマとしての表出に思い切って舵を切っている、という印象。

- ブルーノ・ワルター (指揮)
- ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
- 1938年 ライブ録音
何しろ古いモノラル録音だけど、1950年代の録音と言われても、信じてしまうくらいの音質ではある。これだけを聴いてワルターの解釈を語るのは無謀かもしれないが、楽しむことはできる。
古い録音からでも、艶やかな高弦の歌いっぷりは訴えかけてくる。当日のホール内では、魅惑的な音色が響き渡っていたに違いない、と思わせる。そういう要素をこの交響曲に求めるのかはともかく、その芸に魅力を覚える。
ワルターの気合がストレートに伝わってくる。何よりも、彼によると思しき、オーケストラに拍車をかけるような発声が、頻繁に聴かれる。
音楽の進行に畳み掛ける勢いがある。それでいて、線の一つ一つ、一撃一撃に気持ちが入っている。一音一音に気持ちを込めることと、畳み掛けることは必ずしも両立しない。ギリギリのところまで己れとオーケストラを追い込んでいる感じ。第三楽章の終盤は勢い余っては空回り気味だったりもする。
終楽章は、速いテンポで、かつ浅い呼吸で流暢に進められる。気持ちのこもった強い表現だけど、呼吸が浅いせいで、スケール感はさほどでもない。スケールがデカければいいというものではないから、それ自体は良いのだけど、第一楽章とのバランスで言うと、やや軽くなる。その結果、交響曲の規模としてはいくらか小ぶりに感じられるかもしれない。これは、マーラーの構想に沿っているのだろうか。それともワルターの個性だろうか。
第一楽章は、曲自体がドラマティックな作りになっているから、ワルターの気迫があいまって、聴き応えがある。フレーズの一つ一つに気合が込められているし、緊迫しながらも、語り口のうまさを聴かせてくれる。けっこうテンポは動くし、細かい変化は多いけれど、自然な進行を乱すことはなくて、メリハリと生気をもたらしている。
温度感の高い演奏にもかかわらず、音響の見通しは一定レベルに保たれている。これだけ激しくやりながらも、盛り上がる場面で爆発的な音響でテクスチュアを塗りつぶす、ということをしていない。金管や打楽器などボリュームの大きな楽器は、凄みを効かせつつも、音量はコントロールされていて、他のパートを圧倒することはない(原則として)。
大音量や威嚇的なサウンドによらず、合奏に漲る緊張感や気迫で聴き手を巻き込み、圧倒しようという姿勢を感じる。そのぶん、サウンドイメージとしてのスケール感は控えめかもしれない。それでも、魂の入った密度の濃いアンサンブルはビンビン響いてくる。