音楽鑑賞の備忘録。
| クラウディオ・アバド(指揮) | ヨーロッパ室内管弦楽団 | [1987年 セッション録音] | |
| ヨゼフ・クリップス(指揮) | ウィーン交響楽団 | [1972年 ライブ録音] | |
| オットー・クレンペラー(指揮) | フィルハーモニア管弦楽団 | [1960年 セッション録音] | |
| セルジウ・チェリビダッケ(指揮) | ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団 | [1994年 ライブ録音] |
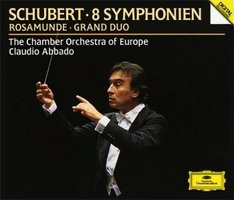
- クラウディオ・アバド (指揮)
- ヨーロッパ室内管弦楽団
- 1987年 セッション録音
シューベルトの自筆譜による演奏とのふれこみ。第二、第三楽章に「オヤッ!?」という部分的な違いがあるものの、作品観を揺るがすような違いではない。
室内楽的バランスによる精細でイキイキとしたアンサンブルが気持ちいい。
編成の大きなオーケストラだと、木管楽器は弦群の大ぶりな響きの波間に漂いがちだけど、ここでは木管群と弦群は対等に扱われている。木管群の積極参加によってアンサンブルのバリエーションは格段に豊かになっている。
フレーズの線をすっきりと浮かび上がらせる。その一本一本が透明な光沢を放ちながら、流麗かつ切れ良く歌い回される。にじみ、くすみ、湿り気を感じさせない、見通しの良さ。感覚的にも機能的にも突き詰められた、それでいて息苦しくも堅苦しくもならないアバドの独自の境地ではないだろうか。
ときに豪快に、ときに沈み込むように、ときに染みるように・・・みたいな、場面に応じた表現の幅はあるけれど、それ以上に、光沢を放つような明るい響きとか、洗練された様式美とかを追求している、ように聴こえる。
その意味で、表情の豊かさを楽しむより、アバドの洗練された技芸を満喫する演奏、という気がする。
当代きっての指揮台のヴィルトオーソの一人であるアバドが(私見)、高性能オーケストラを駆って、磨かれた室内楽的アンサンブルを繰り広げる様を。

- ヨゼフ・クリップス (指揮)
- ウィーン交響楽団
- 1972年のライブ録音
鮮明なステレオ録音。このレーベル特有の艶消しされた響きは、この演奏にとっては残念だけど、それ以外はストレス無く楽しめる音質。
ちょっと聴いたところでは、歌心と見通しの良い響きは印象的ながら、総合的な印象としては、穏当で円満。どこか野暮ったくもあるような感じ。
しかし、個人的には、聴き始めるとジワジワと染みたわってきて、聴き返すたびに感銘を新たにしてしまう。
歌うように弾むリズム、踊るようなメロディみたいな流儀がすみずみにまで浸透している。こういうのをウィーン風と呼ぶのかもしれない。
この交響曲については、彼らの流儀には実利がある、と思う。アンサンブルの線の動きを浮き上がらせ、リズムをしっかり刻みながら、機械的な単調さに陥ることも、音楽を角張らせることもなく、多彩な抑揚を施すことができる。
同じような音型が繰り返される終楽章は、とかく一本調子に響きやすい音楽だけど、クリップスはややゆとりのあるテンポで、あらゆる音型にしなやかな躍動を施していく。高弦の変幻自在の動き。気合いも乗っている。
そして、全身を使って舞い踊るような第三楽章中間部(トリオ)!歌いまくる木管たち。
ただし、演奏全体として捉えると、こじゃれた音楽を優雅にやっている印象はない。
各パートが絡み合う様を実直に描き上げているし、推進力とか、力感だってかなりのもの。重量級まではいかないけれど、サウンドの厚みもそりなりにある。
クリップスはある種の流儀の使い手ではあるけれど、感覚的な愉悦に走るのでなく、実直で手応えのある音楽を指向している、ような気がする。

- オットー・クレンペラー (指揮)
- フィルハーモニア管弦楽団
- 1960年のセッション録音
この時期の録音としてはとても優れた音質。オーケストラのサウンドが一体として響きながら、細部まで聴き取ることができる。
この指揮者らしく、楽曲の骨格を堅牢に組み上げて、画然として明解なアンサンブルを繰り広げている。
規模の大きなオーケストラを明解に鳴らすのに程よいくらいの堂々としたテンポ。大ぶりながら締まった印象を受ける。
歌い上げるとか、リズムを快適に揺らす、みたいなことはなく、整然とブレなく形作られている。
それでも、かなり動的な音楽になっているのは、メリハリの効いた音型の抑揚とか(たとえば、序奏部分は、歌うような節回しではないけれど、抑揚ははっきりとつけられている)、多様なリズムの浮かび上がらせ方のおかげだろう。
音楽全体をリズミカルに弾ませるというのではなくて、ドンと構えた枠組みの中で、それぞれのパートを多彩に弾ませる感じ。
クレンペラー流の妙味が分かりやすく表れていると思えるのが終楽章。
室内楽的というのではなく、ある程度大きな編成を立体的に鳴らして、各パートの動きを際立たせている。
管弦楽のテクスチュアを明解に保ったままで、豪快に盛り上げる。盛り上がる場面でもサウンドが塊にならず、各声部の表情が浮かび上がっているから、全パートを鳴らし切ったような解放感を満喫できる。
一方、第二楽章あたりは、好みが分かれそう。
この楽章は、チャーミングだけど、交響曲の楽章としてはとてもシンプルな造り。クレンペラーは、歌い回しの妙とか、リズムの変化を付けるみたいな、後付け演出をやらないから、シンプルなものをシンプルなままに聴かせる。
ところで、第三楽章の中間部分(トリオ)では、他の演奏とオーケストレーションが異なっているように聴こえる。クレンペラー独自の加筆修正なのだろうか。
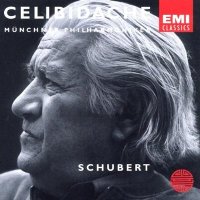
- セルジウ・チェリビダッケ (指揮)
- ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団
- 1994年 ライブ録音
悠々とした足取りに広がりあるサウンド・イメージ。ガッチリとした柄の大きな造形。一方フレージングにもサウンドにも柔らかみがあって当たりは優しい。硬い音、激しい音は遠ざけられている。
しっとりと磨かれた音響美を堪能できる。雄弁な仕上がり。個々のパートはたっぷりと響きながら歌うけれど、骨格が大きいので、ディテールは手に取るように聴こえる。
一方、躍動感とか歯切れ良い切り込みとか激しい高まり、みたいなものはない。悠然とした足取りや量感たっぷりのサウンドの中に、そうしたもろもろが吸収されている感じ。まったりに近い滔々たる流れと音響美に身を委ね続ける、というのが正しい聴き方だろうか?
チェリビダッケの流儀は洗練され、徹底されているけれど、それゆえに楽曲の持ち味のある部分は骨抜きにされていて、表情の幅は狭まっているかもしれない。
要するに、全曲がチェリビダッケ色に染め上げられている感じ。個性的という枠を超えて、自分の美意識で楽曲を染め尽くしてしまった、とでも言うような。
そういう演奏にありがちなこととして、聴き手を選ぶ傾向は強いと感じるけれど、表現者としてのチェリビダッケの存在感は大きい。